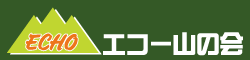| コメント |
西国分寺駅から歩き始め、ほどなく東福寺に着いた。ここには傾城の墓と一葉松が残されている。恋ヶ窪には鎌倉時代の武将畠山重忠と、遊女夙妻太夫の悲恋物語が伝わっている。傾城とは、恋に破れて池に身をなげた遊女のことである。人々は彼女を哀れみ、墓の横に1本の松を植えた。恋ヶ窪という地名は、この悲恋物語に由来するとの事である。また恋ヶ窪は、戦後の混乱期を描いた大岡昇平の「武蔵野夫人」の舞台となった場所でもある。東福寺から清流に沿って姿見の池へ向かう。その清流に手で触れると、その冷たいことに驚いた。姿見の池は、東山道武蔵路の宿場があり、宿の遊女たちが朝夕その姿を池に映し、お化粧したとの言い伝えがある。今では緋鯉や真鯉がゆうゆうと泳いでいて、その面影はない。日差しが強く、道路の日陰や木陰を探して伝え歩いた。またエアコンの効いた市民センターやコンビニなどに立ち寄り、涼を求めた。予定していた殿ヶ谷戸庭園は、時間の関係で割愛した。そこから国分寺崖線の急な道路を下ると、ふたたび野川に出る。そこで真姿の池湧水群から流れくる清流に沿って「お鷹の道」を歩いた。この道沿いには野菜の直売所やお宅カフェがたくさんある。家族総出で働いている野菜の直売所に立ち寄った。数ヶ所に畑をもっているが、畑に行って野菜を育て、収穫するのが大変だと言っていた。十数種類の野菜を販売していて、オクラやゴーヤなどを買い求めた人もいた。ここが、本日の訪問地の中で、みんなが一番生き生きとしていたように見えた。真姿の池湧水群はほど近い。真姿の池湧水群は、環境省の名水百選の一つに選ばれている。段丘崖の裾から豊富な地下水が湧出していて、澄んだ池を作り、弁財天が祀られている。その昔、玉造小町が難病から快癒し、もとの真姿に戻ったという伝説が残されている。武蔵国分寺跡に着いて、広い草原の樹下で昼食とした。武蔵国分寺は、全国の国分寺のなかでも最大規模で、七重の塔や伽藍が林立していたと言われる。新田義貞の鎌倉攻めの際に全て消失し、今は石碑と礎石を残すのみである。昼食後、帰路についたが、足の痛みを訴える人も出たので、タクシーを呼んで西国分寺駅に向かい、炎天下でのウォーキングの達成感とともに反省点も感じつつ駅前で解散した。 |